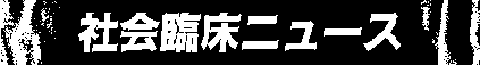
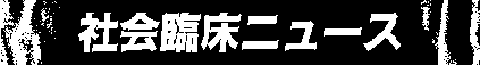 |
|
第50号
|
2003年11月24日 |
|---|---|
| 発行◆日本社会臨床学会 |
〒310-8512 茨城県水戸市文京2-1-1 茨城大学教育学部情報文化教室林研究室 |
E-Mail:shakai_rinsho@yahoo.co.jp FAX:029-228-8314 TEL:090-3143-5988 |
|
| 年会費6000円 | 郵便振替:00170-9-707357 銀行:みずほ銀行東陽町支店(普通)8013029 |
現在、社会臨床学会には、1998年3月に、『社会臨床雑誌』第5巻別冊として作成した会員名簿があります。しかし、数年を経過するなかで、会員の、入会や脱会、あるいは住所や職場などの変更があり、現在の会員名簿が会員の現状を反映していないことから、新しい会員名簿を作成することが第?期運営委員会からの継続課題となっていました。以上の経過を踏まえて、新たに会員名簿を作成します。
新たに名簿を作成するにあたり、運営委員会で話し合って、その趣旨を、(1)会員の現状を反映すること、(2)会員相互の理解と交流のきっかけになること、におきました。社会臨床学会の会員がどのような場で、どのような領域に関心を持ち、そしてどのような活動をしているのか、などが少しでもお互いにわかれば、何かの折に連絡をとって交流する機会が生じるだろうということです。同封した名簿作成のための用紙をご覧頂ければお分かりになると思いますが、これらの名簿作成の趣旨から、とりわけ「関心のある領域・一言」欄へのご記入をよろしくお願いしたいと思いますし、所属欄は必ずしも職場名称ということではなく、ご自身にとって活動などの中心になっている場を記入して頂くことでも構いません。もちろん、掲載不可の項目があれば、その旨をお知らせいただけるようになっています。
これらの趣旨について、会員のみなさんのご理解とご了解を頂き、会員名簿の作成にご協力をよろしくお願い致します。
同封の名簿作成のための用紙にある記入要領にそって必要事項をご記入ください。また、返信用封筒も同封してありますのでご利用ください。
返信の期限は、2003年12月末日必着でよろしくご協力くださいますよう、お願い致します。期限までに返信が無い場合、現在の名簿に記載されているものと同じ内容で掲載可と考えますので、変更や掲載不可の項目がある方はご返信いただきますようにお願い致します。
なお、ご不明の点などございましたら、学会事務局までお問い合わせください。
来年の日本社会臨床学会総会は関東地域での開催です。
会場予約の手続きの関係で、最終的な確定はできていませんが、以下のように予定していますので、お知らせいたします。確定あるいは変更が生じましたら、すぐに『社会臨床ニュース』でお知らせいたします。
プログラムは、定期総会の他に、記念講演と、全体会形式での2つのシンポジウムを予定しています。シンポジウムは以下の予定です。
まもなく法案成立の可能性がある教育基本法「改正」をめぐって、その「改正」が向かおうとしている方向を広角的かつ批判的に検討する。愛国心やグローバリズムなどが同時に主張されるなかでの教育基本法「改正」に潜む思想的な意味、またこの「改正」への賛成・反対にかかわらず前提とされがちな“教育は良いもの”という考え方が持つ問題点、さらに健康増進法の法制化や憲法「改正」論議など、昨今の他の法制化等の動きと教育基本法「改正」の関係を考えていく。
社会臨床学会は、臨床心理学的な営為に対する自己点検を、臨床心理学会改革路線からの継承テーマとして位置づけ、近年の心理ブームなどに見られる社会の心理主義化に対しても批判的な検討を行なってきた。最近になって、社会の心理主義化に対する批判的言説があちこちで急速に展開されつつある。いま、もう一度、社会臨床学会での心理主義化批判を問いなおしていきたい。
2003年9月13日(土)・14日(日)・15日(月)に、長野県原村の「まさかロッジ」にて、おいしい食事と明媚な風景を楽しみながら、合宿学習会を持ちました。学習会の報告は、『社会臨床雑誌』に改めて掲載する予定です。本号ニュースでは、2つの学習会の司会者に感想風にまとめていただき、また参加者から合宿参加の感想を寄せていただきました。
初日の9月13日午後行われたシンポジウムは教育基本法「改正」問題を中心に教育改革の動向をどう捉え、批判していくのかという点がテーマです。発題者は東京都足立区立第5中学校の戸恒和夫さんと関西大学の岡村達雄さんです。
戸恒さんは、「日の丸」の常時掲揚が強制され、都立高校改革推進計画が実施され、都教組が分裂した1997年以降の東京都の「教育改革」の動きと問題点を、ご自身の経験を交えながら、克明に報告しました。この「改革」は教員にはゆとりではなく、忙しさと管理強化をもたらすだけだったと。戸恒さんは1週間に3時間だけしか空き時間がない状態だそうです。こういった状況の中では、自分たちで何かを頑張ってやっていこうという気はつぶされていき、言われたことをその通りにすればよいという雰囲気が満ちていく、と戸恒さんは言います。
岡村さんは、教育基本法を擁護するのではなく、教育基本法の限界を指摘するところから教育基本法「改正」問題を考えます。教育基本法1条には「教育目的」が記載されており、既に法によって心を律するという視点が入いりこんでいます。このような基本法を擁護する視点からは、国家と心の関係を再定義しようとする目的をもつ教育基本法「改正」問題をきちんと捉ええることはできない、と岡村さんは指摘します。そして、この心と国家の再定義は文部科学省が出した「教育の構造改革」の中にはっきりと表現されていると説きます。
お二人の発題の後2時間にわたって熱気のこもった討論が行われました。残念ながらここで紹介することはできませんが、『社会臨床雑誌』で岡村さん、戸恒さんの報告とともに議論の一部をご紹介する予定ですので、どうぞ御参照下さい。(中島)
おりしも火星大接近を迎えていたのでした。長野県原村は日本でも指折りの、星が美しく見える場所のひとつなのだそうです。私達の学習会の会場の「自然文化園」の前庭も、陽が沈むと観望会の会場となっていました。
「大接近」と言っても、火星は小さな赤い点でした。何千キロ、何万キロという彼方に浮かんでいるのであろう火星と、同じように銀河系の外れにほんの一時ポカンと浮かんでいる地球の姿を思い浮かべると、私達の思いなんて何ほどのものなのだろうと思わずにはいられません。
それでも私達は今のこの場所を生きるしかなく、塵芥(ちりあくた)の成り行きに一喜一憂する存在でしかないのでした。
さて。学習会の司会を担当した私は、ここで八〇〇字ほどで当日の感想めいた報告をすることを求められました。
久しぶりの二泊三日の合宿だったのですが多くの人が一泊で帰るということで、二日目のこの学習会は急遽時間を変更して開催しました。何年か前、同じ場所で行なった合宿のことを思い起こすと、人々の暮らしがここ数年の間ですら慌ただしくなっていることの現れなのだろうか、等と考えたりしました。
参加者の発言を聞きながら感じたことのひとつは、「専門性批判」であって「専門性否定」ではないという点はいつのまにかはっきりしていたのだなということでした。かつては「専門性否定」というようなナイーブな議論もあったようにも思うのですが、専門性の問題の起点には「専門性」をどう定義するかの問題があるのであって、「専門性」という概念を否定するということは、「『専門性』を否定する」と言ってしまった瞬間に不可能になっているということが共通了解になってきたように思いました。この点が明確になると、専門性批判の議論は、専門性の権力構造の解明、専門性の権力の制限、専門家に頼らないという個々人のライフスタイル、専門家との関わり方のHow To、といったものに収斂してゆきます。言い換えれば、「専門家に好き勝手させないための方法」と「専門家との上手な付き合い方」、専門家の側から言えば「ユーザー主体の専門家になること」「倫理観を持った専門家になること」という話です。こういう状況が良いことなのか、悪いことなのか、僕にはすぐには判断できません。
字数もかなりオーバーしました。このあたりでお暇します。(林)
とても「お気楽」に合宿に参加したので、明るく「合宿の感想を書いてね」と依頼された時は正直な所「困ったなあ」であった。でも折角の機会だ、上手く行くか解らないが、文字にしてみるのもよいかもしれない。
一つ目の学習会は教育改革がテーマだった。教育基本法「改正」がある事は知っていた。大概の物が「改正」される時って、その殆どが「これって『改悪』って言うんじゃあないの?」と思う事が多いから、今回の教育基本法もきっと「改悪」に違いないと思っていた。が、日々の雑事に追われて余りよく考えもせずにいた。だから、想像以上に「改悪」されている事実に驚いた。
特に、意見交換の中で出て来た「心のノート」の存在は知らなかったので、その内容のヒドさに呆れた。ただ単に知らなかった!では済まされないような内容ではないか! 一体いつ何処でこのような冊子が作られる事は決まったのだろう? 私の知らない所で、税金を勝手に使ってこんなモン作って!と腹が立って来た。ボンヤリと生活していたらドンドン私の望まない方向へ社会が動いて行ってしまう!と反省、反省だった。
小沢さんがおっしゃっていた教育基本法の「改悪(と言ってしまおう)」の尻馬に乗るようにジェンダーフリーバッシングも起きているという事は、思いもかけない所で問題が繋がっているんだなあと、目から鱗状態だった。一つの問題が投げかけられた時に多角的に考えたり見たりしないと駄目なのね、とつくづく感じたのである。
二つ目の学習会のテーマ、心理職の資格化について。このテーマは、私の勝手な感想かもしれないが、社臨の生みの母だと言ってしまっても構わないのではないの?と思う位、これまでも度々赤松さんを始めとする、ケースワークの仕事に携わっていらっしゃる方々から、患者さんの叫び声や心の痛みがヒシヒシと伝わってくるようなお話を聞かせて頂いて来た。実際にはその声はなかなか届かないって、悲しい報告な事が多い。患者さん達にとって良くなる事を主張している声なのに。
本当ならうんざりとしてしまうはずなのに、でも、赤松さん達は諦めていない。その不屈な思いが今回は特に、私の心に響いてきた。何故なら、最近の私には「どうせ私はマイノリティよ」「暮らしにくくて意地の悪い生活の方を皆が求めているんだから仕方ないじゃない」と開き直っているような部分があるからなのだ。今回、また赤松さんと佐藤さんのお話を聞かせて頂いて、開き直りがちな私の気持ちをもう一回「畳み直して」みようと思った。
一日目の学習会の最中に夕立ちが来た。その後にとても綺麗な虹がかかった。二日目の夜は、雲がちょっとあったが、久々に天の川や、夏の大三角などを観る事が出来た。合宿の参加者の方々がそれぞれの立場で力強く生活をしていらっしゃる、その姿も見せて頂いた。私の気持ちもちょっとスッキリとした気持ちになった気がする合宿だったと思う。参加者の皆様、どうもありがとう。
私が社臨に入ったのは3年前で、とても重要な問題が、さまざまな現場の人を交えて議論されているのがわかり、一言も聞きもらすまいと熱心に参加している。いつも、そのつど心を打たれ、衝撃を受ける。懇親会等には参加したことがなかったが、今回初めて夏期合宿に参加した。
美しい高原の花が色とりどりに咲いている長野県原村の自然文化園の会議室で、涼しい風にふかれながら、また園の子どもの歓声が聞こえるなか、くつろいだ雰囲気で二日間発表や議論がなされた。内容はいつもと同様にシビアなものであり、初日は、戸恒さんの、「教育改革」の流れの中で、と題された1997年からの教育現場の変化と問題点が、具体的にかつ詳細に示され議論された。岡村さんの「『教育の構造改革』と教育基本法『改正』」では、文部科学省の教育の構造改革のもつ問題点が議論され、さまざまな教育現場からの関連ある議論がなされた。翌日は、佐藤さんの臨床的営為と倫理について、次いで赤松さんご自身の40年間の医療経験、現在の医療保健心理士資格化に関する話がなされた。多くの論点が示され、また二日間の話は関連してぴったりかみあっていた。
夜は、宿泊場所のまさかロッジで、さまざまな地元のごちそうの夕食をいただき、温泉にも入った後、自己紹介を含めながら、ビールを飲みながらの夜の議論の場が用意されていた。じっくり、いろいろな方とお話しができて、夜おそくまで、各自が考えていることを親しく語ることができるのは、やはり「共に」同じ所に宿泊しているという場のもつ作用であろう。社臨では、この合宿形態を大事にしている意味がよくわかった。
ちなみに、私が他に属している学会は、大学院生たちのデビューの場であり、研究者集団の発表のみのプレーンなもの。社臨のように、現場や当事者の声による議論の重層性、現在最も問題となっている点を考えるという現代性、学会のもつ儀礼性や政治性を排除して、純粋にそのことだけを議論すれば、いかに実りある議論がなされ、すばらしいかがわかる。社臨のメンバーは、「弱者ではなく、強者ではないか」という声が出されたが、いろいろな圧力に屈せず自分の考えを通し、問題提起をしながら生きてこられた姿にピュアさと「共に生きる」という言葉どおりのやさしさを感じた。
「臨床」という語についても必要かどうか議論がなされた。いろいろ意味づけがあろうが、「臨床」とはさまざまな立場の人が交じりながら考え、できるだけ現場に近く、当事者の視点から現実を見るという姿勢だとすれば(拙稿「臨床社会学のパースペクティブ」『臨床社会学を学ぶ人のために』、世界思想社)社臨はやはり、真の意味で望ましい形での「臨床」というタームがあるならば、それにぴったりとふさわしいと感じる。
本号には、お知らせが二つあります。一つは、学会でも学習会を開き、また反対声明も出した「心神喪失者医療観察法案」に関連するもの、もう一つは、教育改革基本法「改正」反対に関連する講演会、集会のお知らせです。
保安処分新設立法・予防拘禁法「心神喪失者医療観察法」の成立を怒りをもって糾弾します。この法制定を受けて、今政府は法の発動に向け、政・省令や審判規則整備、国立武蔵病院・肥前療養所など保安処分病棟設置、医者・看護師・ケースワーカーの研修など保安処分体制作りに動き始めています。
私たちは希代の悪法の成立を許しました。しかし、法案阻止を闘ってきた精神障害者、医療従事者、労働者、市民、弁護士、学者など、さまざまな領域を超えた仲間が、約2年に及ぶ闘いの中で、これからも精神障害者差別を許さず、共に生き、共に闘っていける可能性を確信できたことは、闘いの中で獲得したかけがえのない成果でした。その成果をさらに発展させ、保安処分体制構築・法の発動を許さない闘いへ、新たに踏み出していくことが今求められています。
そのような新たな闘いに向けて緩やかな交流・連帯・共闘を目指す「予防拘禁法を許すな!ネットワーク」(仮称)を結成していきたいと思います。
多くの皆さんの参加を要請します。
| 名称: | 「予防拘禁法を許すな!ネットワーク」(仮称) |
| 目的: | 法の発動を許さず廃止を目指しつつ、保安処分を許さないさまざまな闘いを闘う幅広い・緩やかな交流・連帯・共闘を目指す |
| 取り組み内容: | ・ 運営や具体的な闘いの提起などは今後の議論の中で ・ 保安処分体制構築と法の発動を許さない活動 ・ 学習・討論会活動 ・ 情報の交換・共有化(通信の発行を含め) |
| 年会費: | 団体一口1000円以上、個人500円以上 |
ご参加いただける方は下記連絡先まで、以下の事項をお知らせください。
氏名(団体・個人)、連絡先、住所、電話番号、ファックス、e-mail、年会費(口数と金額)、また団体・個人か、公表の可・不可をお書き添えください。
また、廃案闘争の記録集『閉じ込めないで!もうこれ以上』(B5判 128ページ 500円)のご購読をよろしくお願いします。なんと、500円の大特価。この売り上げ利益をとりあえずのネットワーク運営資金といたします。600部売れてやっと印刷費用が出ますが、それ以上売れないとネットワーク運営費が出ません。各地の皆様、なにとぞまとめてお買い上げを。お申し込みはネットワーク連絡先まで。送料も合わせてお振込み下さい。送料は1冊290円、5冊450円、10冊590円です。お振込みの際はパンフ代かネットワーク会費かを明記してください。
| 講 師 | 大内 裕和さん(松山大学 教育社会学) |
| と き | 12月7日(日)13時30分〜 |
| ところ | 埼玉県戸田市新曽福祉センター 2F講習会室 (埼玉県戸田市大字新曽1395 TEL048-445-1811) 埼京線戸田駅より約900m(徒歩12分) |
| 主 催 | 「教育基本法改悪」に反対する埼玉行動賛同者 |
| 参加費 | 無料 |
「12.23教育基本法改悪反対全国集会」に賛同して、埼玉で、教育基本法改悪につながる現行の「教育改革」の正体や、関連する様々な状況を明らかにしていく行動です。
| 連絡先: | 戸田東中学校内 戸田教職員組合 戸田市下戸田1−11−15 toda_kyouso@yahoo.co.jp (電話でのご連絡はご遠慮ください) |
様々な団体や個人が、お互いの違いを尊重しつつ、教育基本法「改悪」反対の一点に賛同して行なう全国集会です。各団体や個人は、全国集会へ向けてそれぞれの立場で活動を積み上げていき、全国集会後にはそれぞれさらに活動を広げていきます。その全ての活動が、全国集会の一部でもあるのです。
正確な趣旨は、呼びかけ人4氏(大内裕和、小森陽一、高橋哲哉、三宅晶子)の呼びかけ文をご覧ください。
| 全国集会 場 所: | 東京 日比谷公会堂 |
| 日 時: | 12月23日(火・休) 11時半会場 12時半開演 (集会前に日比谷公園でパフォーマンス、集会後にパレードを予定) |
| 参加費: | 無料(集会は賛同金とカンパでつくれられています) |
| 主催者: | 教育基本法改悪反対!12・23全国集会実行委員会 連 絡 先:〒113-0033 東京都文京区本郷5−19−6 坪井法律事務所内 TEL&FAX 03-3812-5510(平日午後2時〜5時以外は留守番電話) |
| 呼びかけ文掲載サイト: | http://www.ne.jp/asahi/kyokasho/net21/top_f.htmで 「■教育基本法改悪反対!12・23全国集会」をクリック。 |
埼玉行動では、講演会参加者と、埼玉行動への賛同者を募集しています。埼玉行動賛同者の賛同金は無料です。賛同者としての氏名等の公表と非公表が選べます。賛同してくださる方は、上記連絡先へご連絡ください。
全国集会でも、集会参加者と賛同者を募集しています。全国集会賛同者の賛同金は、1口500円原則2口以上、団体1口2000円です。上記連絡先へ、ご連絡ください。こちらも、賛同者としての氏名等の公表と非公表が選べます。